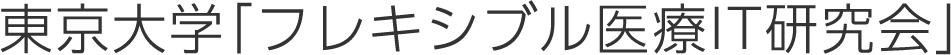フォーラムへの返信
-
投稿者投稿
-
東レエンジニアリングの坂上です。
環境にセンサを配置して、生体情報をセンシングする方法に関して、もう少し考えてみました。
このような仕組みを実現する場合、机、いす、ドアノブなどの既存の環境にセンサを配置することになると考えました。そうすると、様々な形状がありますので、硬いセンサでは配置が難しく、また触れた時に違和感があるなどヒトとの親和性が低いという問題が考えられます。その点、皮膚上にプリントできるほど柔軟なセンサであれば、様々な形状に配置することが可能で、触ったときの違和感も小さく、ヒトとの親和性が高くなることから、フレキシブルデバイスが重要になると考えました。
こういったことから、未病対応のためには、日常生活環境でヒトが意識することなく、さりげない計測を実現するために、フレキシブルデバイスが重要になる、と思いました。東レエンジニアリングの池田です。
投稿が直前になりすみません。
クリステンセン先生のジョブ理論から、何故にそのデバイスを必要とするかという目線で考えてみました。
フレキシブルを必要としないニーズにフレキシブルを提案しても意味がないし、軽さを必要としないのに軽量化の説明は無意味です。
この点で、今回のお題目は誰の目線で考えるかによって提案内容は全然異なると思います。
不十分ですがファイルに記載しました。
また、前回のワークグループにて、筋肉トレーニングの効果を指標化する技術について説明しましたので、この技術の簡易内容も添付します。
当該技術の出口を探している状況なのでご指摘いただければ幸いです。Attachments:
You must be logged in to view attached files.東レエンジニアリングの坂上です。
未病対応に関して、フレイルや関連するロコモティブシンドローム、サルコペニアは今後ますます注目されると思います。
これらは、飯島先生の「ゼロ次予防」という概念もあり、生活習慣病と同様に日々の生活が予防に大きな役割を果たすと思い、以下のように考えました。必要な機能:日常生活環境での活動量とバイタルデータ(心拍、呼吸、体温、血圧)の計測
活動量はどの程度運動しているかを、周りの人が定量的に把握するために必要で、バイタルデータは虚弱化を周りの人が早期に発見するために必要と考えました。データを利用するのは、センシングされている人ではなく、その周囲の人(家族、友人、医療者など)や何らかのサービスかなと思いました。24時間連続モニタリングが理想的と思いますが、数時間ごとの間欠データでもよい(例えば、食事で椅子に座ったとき、トイレで便座に座ったとき、散歩で靴を履いた時など)と思いました。そうなるとウェアラブルセンサを人に配置するのではなく、環境に配置するでもよく、それらのセンサで得たデータを集めるデバイスが重要になると思います。センシングされている人は、それを意識しない仕組みが重要なので、ポケモンGoのようなゲーム性の高いアプリが有用かと思いました。今でもたくさんのユーザがいますが、歩くことを目的としてプレイしているユーザーは少ないと思いますが、結果的にたくさん歩いて健康側に行動が変容できている場合もあると思います。やはり人を選ぶことになりますので、万人に受け入れられる仕組みや、繋がりをセンシングする方法の実現が課題だと思います。
東レエンジニアリングの池田です。
大阪商工会議所主催の次世代医療システム産業化フォーラムの第5回例会(明日10/21開催)での医工連携マッチングテーマに添付の提案がありました。
具体的な例としてFMITメンバーで共同開発テーマとして、提案内容を上回る提案ができればと思いますがどうでしょうか。Attachments:
You must be logged in to view attached files.東レエンジニアリングの池田です。
また、直前の投稿で申し訳ありません。クラボウ・東様の描かれたマップイメージを基に、エスケーエレクトロニクス・広中様のご提案内容を小職なりに拡張したマというップイメージを作成しましたので添付します。
1.求められる機能・性能
現在議論の中心にあるのは、「フレキシブル」=「ウエアラブル」という視点であるように思いますが、体に「身につける」
という観点では、一時的(使うとき)に手に持つ、重いので常時身につけたくはないが必要な時に装着できるという
インターフェース(デバイス)も求められる機能ではないかと思います。
最終的(ゴール)は重たい・かさばるデバイスも軽量化・フレキシブル化してインターフェースと一体化したデバイスとなりますが、
技術レベル的に段階を踏むとすれば、各種センサーデバイス等を簡単に接続可能なインターフェースデバイスではないかと考えます。貼るデバイスを考える上では、「貼れる」ことは技術的には意義はありますが、ユーザにとっては「必要があるから」貼るのであって、
ユーザの目的に合わなければ価値はありません。また現在のヘルスケアデバイスは、ほぼ全てがパーソナルヘルスを計測記録するパーソナルヘルスケアデバイスであると思われますが、
今後もこのトレンドは継続拡大すると思いますが、一方で現在のコロナウイルス対応を考えるとパーソナルマネジメントではなく、
集団を計測・記録するポピュレーションヘルスケアマネジメントが必要であることが明確になりました。
このポピュレーションヘルスケアマネジメントが可能となる機能・デバイスが必要となると思われます。2.技術の芽
一時的に「手に持つ」というデバイスにボールペン等の筆記具があります。
一方で現在は高級腕時計で重用されている幾世代前の「自動巻」というエネルギーハーベスティングデバイスがあります。
現在のMEMS時代の「自動巻MEMS」をボールペンに組み込めば、筆記することで発電し指や掌に受電・信号インターフェースがあれば
センサーデータを外部発信やボールペンの中に記録できるのでないかと思います。
「フレキシブル」=「ウエアラブル」という観念レベルを下げて、一時的に「持つ・身につける」という見方をすれば
フレキシブルデバイスの目的が「人の機能の拡張」であるならば、いろいろ出てくるように思われます。Attachments:
You must be logged in to view attached files.お世話になっております。
東レエンジニアリングの坂上です。本日の検討資料をアップロードいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。Attachments:
You must be logged in to view attached files.東レエンジニアリングの池田です。
本日の研究会のことが頭から外れていました。
急ぎ宿題について以下の様に考えています。(1)今後、5年から10年の間の社会変革が進む中で、 医療・ヘルスケアに対して新しく要求される事、 要求の重要性が増す機能や性能は何か?
医療とヘルスケアの垣根がクロスではなく、分化してゆくのではないかと考えます。
現在のヘルスケア・医療の境界にあるような技術・製品は医療用としては、現在よりも厳格な管理運用が求められ、医師の指示により使用され、
患者の好み・趣味で使用される機器ではさらになくなり、使用方法も限定(指示)されると考えます。
ヘルスケア製品はより使用者の好み・趣味に合わせるような方向性になるように思われます。(2)まだ研究開発段階で実用化はされていない、 もしくは実用化が進んでいないが、 今後の医療・ヘルスケアで重要と考える技術の芽は何か?
ビフィズス菌に代表される大腸菌、腸内細菌の機能の解明、及び活用ではないかと考えています。
人間の体を構成する細胞数は39兆個(以前は60兆個とされていた)に対して、共生する腸内細菌数は100兆個とされており、人が体内臓器では生成
しえない栄養源やエネルギーを産生して、腸内細菌には住みやすい環境(嫌気性等)を与えています。
感染症や免疫の機能も大腸が担う部分も多く、新型コロナ感染が日本で深刻になっていない状況も腸内細菌の違いによる免疫機能の差異ではないかと
個人的には考えているところです。(3)WGのターゲットを明確にする。たたき台では「フレキシブルデバイスが刺さる用途と、 それを実現するために必要なブレイクスルーは何かを明確にする」
としています
申し訳ありませんがまだ十分に考察できておりません。
このWGを通して自分なりに解を見いだせればと考えているテーマです。WG開催間際の投稿で申し訳ありません。
WG3メンバーの皆様
東レエンジニアリングの池田です。よろしくお願いいたします。
頂いていた内容については、以下の様に考えていますが、いかがでしょうか。(1)WGの進め方・スケジュール
11月中旬まで2~3週間に1回の頻度でのWGとの原案で良いと思いますが、この日程を第1回WGにて決めたらどうでしょうか。
計画が立て易いと思います。
また、可能であれば最終回は東大に参集して議論できればと思います。(2)WG活動に必要な調査活動
提言目標となる革新的な診断・治療技術はポストコロナも踏まえた、あれば良いという技術・製品ではなく、2025~2030年に必要
となる技術であり、開発を期待される技術・製品ではないかと考えます。
例えば、過疎化・限界集落の問題は拡大すると思いますが、快適性を備えた「新しい住まい方」に資する診断・治療の技術コンセプトも
一つの調査項目かなと思われます。
このような技術コンセプトをWG3にていくつか協議提案して調査する方法はいかがでしょうか。(3)WG活動の参考になると思われる資料のアップロード
5~10年後に必要な技術の参考になる資料などないと思います(あるとすればロードマップの類)が、技術にも何に利用すると良いか
よく分からない技術も多くあり、時期尚早で消えた知らない技術もあると思います。
添付資料は消えた技術ではなく有望とされる技術ですが、このような技術についても色々な角度から見て行ければと思いアップしました。(4)医療・ヘルスケア診断/治療技術の革新にご興味をお持ちになった理由
私は現在スタートアップ企業と共同で手術支援ロボットの開発を行っていますが、20年前は米国では先駆のロボット・ダビンチが開発され
ていましたが、日本国内では高度な手技の手術にロボットなど使えないという意見の医師が大多数(ほぼ全部)でした。
10年前くらいから日本でもロボットの導入が始まっても、大部分の意見は限定用途としか考えていませんでした。
現在は、手術支援ロボットは市民権を得て色々な治療科目への適用が待望されている状況です。
何が変わったのか?
いろいろあると思いますが、酷評されても一つ一つ成果を積み上げて実績をつくってきたこと-革新的な技術は拍手で迎えられる
のではなく、また一夜にして成る技術ではないと思われるので、どのような技術が「革新」であるのか考えてみたいと考えた由です。足手まといにならないように対応したいと思いますが、対応が遅いかもしれません。
どうぞよろしくお願いいたします。
東レエンジニアリング
開発部門・開発部
池田 宗和東レエンジニアリング株式会社の坂上と申します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。・WGの進め方やスケジュールに関するご意見
情報収集が不足しており、ビジョン策定をいつ頃を目標としているのかを把握できておりませんが、
月に1回程度ペースでは、PC会議等でミーティングを行い、皆さんとご意見を交換できればと思います。・WG活動に必要な調査活動
「未病対応」に注目しており、日常的な計測で病気になることを防ぐデバイスや仕組みが作れれば、と考えております。
臨床医のご意見や臨床現場でのニーズなどを調査する必要があるかと思いました。・WG活動の参考になると思われる資料のアップロード(もしくはURLの添付)
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、立命館大学が中心となっているCOIでは下記のような取り組みを実施されています。
「未病対応」を考えた場合、ユーザーは現時点では新しいデバイスや仕組みを使用する必要性に迫られていないため、その技術を生活に
浸透させる工夫が大切だと思いました。
http://www.activeforall.jp/・医療・ヘルスケア診断/治療技術の革新にご興味をお持ちになった理由
若輩者ですが、長く医療・ヘルスケアに関する研究開発に従事して参りました。そのため、この分野に非常に興味を持っております。 -
投稿者投稿